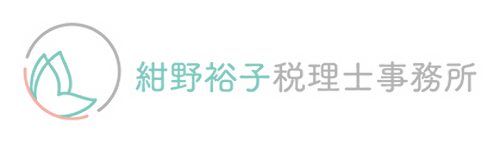#11 リフォーム費用の負担と贈与税の落とし穴
「念願のリフォームが完成!いよいよ新しい生活が始まる!」 喜びも束の間、思わぬところで驚かれる方がいらっしゃいます。特に、ご家族で協力してリフォーム費用を負担したケースでは、知らぬ間に贈与税の対象となってしまうことがあるため注意が必要です。 今回は、リフォーム費用にまつわる贈与税の仕組みと、そのリスクを回避するための具体的な対策について解説いたします。
リフォーム費用負担で贈与税が発生する理由
民法第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
リフォームによって建物の価値が増加した場合、そのリフォーム部分は既存の建物と一体化しているとみなされます。そのため、リフォームによって生じた価値は、建物の所有者のものになります。よって、建物の所有者ではない方がリフォーム費用を負担すると、その負担額は所有者への「贈与」とみなされ、贈与税が課されることになります。年間110万円の基礎控除額を超える部分には贈与税が発生しますが、リフォーム費用の場合、この控除額を超えるケースが大半を占めるでしょう。
具体的な事例で見てみましょう。
- 建物の所有者:夫
- リフォーム費用総額:2,500万円
- 夫の負担:1,000万円(40%)
- 妻の負担:1,000万円(40%)
- 子供の負担:500万円(20%)
このケースでは、妻と子供の負担額 計1,500万円が夫への贈与とみなされます。基礎控除額を差し引いたとしても、およそ450万円もの贈与税が発生することになり、後々大きな負担となりかねません。
しかし、建物の所有者様ご自身の資金だけでリフォーム費用を賄うことが難しい場合でも、多額の贈与税を回避しつつ、ご親族に費用を負担してもらう方法があります。
多額の贈与税を回避する3つの選択肢
ここからは、具体的な税負担軽減策を3つの方法に分けてご紹介します。
1. リフォーム前に建物の「持分」を変更する
この方法は、リフォームに着手する前に、リフォーム費用を負担するご親族へ建物の所有持分を贈与するというものです。
- メリット: リフォーム前の建物は、一般的に築年数や状態から評価額が比較的低くなっていると考えられます。この低い評価額の段階で持分を贈与するので、贈与税の負担が抑えられます。持分を取得した方は、その後、ご自身の持分に応じたリフォーム費用を負担すれば、贈与の問題は生じません。
- 留意点: 所有持分の変更には、不動産登記手続きが必要となり、登録免許税や司法書士への報酬といった別途費用が発生します。また、建物の所有関係が変わるため、将来の相続における影響も考慮し、慎重に検討する必要があります。
2. リフォーム費用を「代物弁済」として持分を譲渡する
リフォーム費用を一旦ご親族に負担してもらい、その費用に代わるものとして、リフォーム後に建物の所有持分を譲渡(売買)する方法です。
- メリット: このケースでは、贈与税ではなく譲渡所得税が課されることになります。譲渡所得の計算においては、建物の取得費等を控除できるため、単純に贈与税を計算するよりも税負担を軽減できる可能性が高いです。また、元の建物とリフォーム後の建物の価値を区別し、それぞれの所有期間に応じて長期譲渡所得・短期譲渡所得として計算します。
- 留意点: こちらも所有者の変更に伴う登記費用等が発生します。また、譲渡所得税の計算は複雑になる可能性があるため、事前に税理士にご相談いただくことを推奨します。
3. リフォーム費用を「貸付金」とする
ご親族からリフォーム費用を負担してもらうのではなく、「貸付」として金銭を借り入れ、計画的に返済していく方法です。
- メリット: 金銭の貸し借りであるため、贈与には該当せず、贈与税は発生しません。
- 留意点: 貸付として成立するためには、建物の所有者に「現実的な返済能力」があることが大前提です。年齢や収入、保有財産を考慮し、無理のない返済計画を立て、金銭消費貸借契約書を作成するなど、客観的に「貸し借り」であることを証明できることが重要です。返済の実態がないと判断された場合、贈与と認定されるリスクがあるため、細心の注意が必要です。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用について
ご夫婦間の贈与では、「贈与税の配偶者控除」(通称:おしどり贈与)の適用を検討される方もいらっしゃるでしょう。これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を「取得」するための資金や不動産そのものを贈与する場合、課税価格から基礎控除とは別に最大2,000万円を控除できるという制度です。
しかし、この制度の適用には注意点があります。
この規定における「取得」には、「建物の増築(床面積が増加する工事)」は含まれますが、「改築等(床面積の増加を伴わない内装や設備の改装など)」は含まれません。
一般的なリフォーム工事は床面積が変わらないものが多く、この配偶者控除の対象外となるケースが多いです。ご自身の行われるリフォーム工事が増築に該当するかどうかは、事前にリフォーム会社にご相談ください。
「住宅取得資金の贈与の特例」や「住宅ローン控除」など、他の税制優遇措置が「増改築」も対象としている一方で、配偶者控除の適用範囲は異なっているのでご注意ください。
まとめ:計画的なリフォームのために
リフォームは、ご家族の夢を形にできる素晴らしい機会です。しかし、その費用の負担方法によっては、思わぬ贈与税の負担が生じる可能性があります。
今回ご紹介した選択肢を参考に、税負担を最小限に抑えながら、安心してリフォームを進めていただければ幸いです。不明な点や具体的なシミュレーションが必要な場合は、ぜひリフォーム前に税理士にご相談ください。