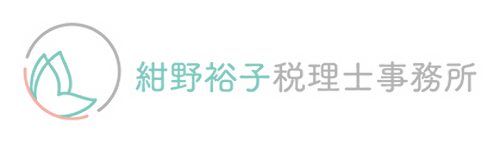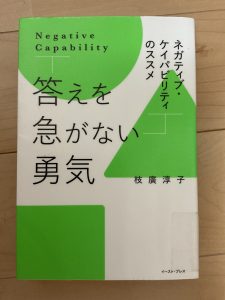#10 株式の取得費の計算方法(持株会での株式の取得費が不明な場合)
株式を譲渡した場合、原則として、譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告が必要です。
(特定口座で源泉徴収されている場合を除きます)今回、20年前に勤務していた会社の株式を譲渡した方から取得費が不明とのことで確定申告のご依頼をいただきました。
持株会で株式を保有していた場合、退職時に、持株会口座からご自身の証券口座に株式が移管されます。その際、源泉徴収ありの特定口座に移管されていれば、基本的に確定申告は不要です。しかし、今回のケースでは、特定口座での譲渡ではあったものの、20年以上前の取得であるため、証券会社でも取得価額に関する記録が保管されておらず、ご自身で確定申告をする必要がありました。
株式の取得費を計算する方法
株式の取得費を計算するには、①取得日と②取得日の株価を把握する必要があります。
まずは、取得日を特定することから始めます。
持株会のケースでは、一般的には給与から毎月一定額が控除され、その金額に応じた株数が積み立てられます。会社からは持株会報告書や退会(引出)計算書が交付されますが、長期間経過していると保管されていないことも多いでしょう。
もし、手を尽くしても取得費を把握することが困難な場合、実務上、持株会からの名義書換日を取得日とすることが、明確かつ簡便な方法として認められています。
今回のケースでは、証券会社から発行された「株式移動証明書」には実質通知日の記載はあるものの、名義書換日の記載はありませんでした。実質通知日は、名義書換日とは異なるため、証券会社へ名義書換日を確認していただきました。
これで、無事、取得日を特定することができました。
概算取得費5%での計算
取得費が不明な場合に、譲渡対価の5%を取得費とみなして計算する方法も認められています。しかし、多くのケースで納税者不利となる可能性が高いと考えられます。概算取得費を使うのは、最終手段と考えた方がいいでしょう。
過去の株価を確認する方法
取得日が確認できたら、次に取得日における株価(終値)を調べます。
まず手軽な方法として、インターネット検索が挙げられます。
「日本取引所グループ」のウェブサイトから、「マーケット情報」>「統計情報(株式関連)」>「東京証券取引所日報」>「株価情報(過去分)」と進むことで、過去の株価を調べることができます。
ところが、株価にたどり着けると思って開いてみたところ、どこを探しても調査対象の会社名が見当たりませんでした。上場後に一度上場廃止となり、再度上場していたというイレギュラーな経緯があったと分かりました。どうやら上場廃止に伴い、過去の株価情報がウェブサイト上から削除されてしまったようです。
残念ながら、インターネットでの確認はできませんでした。
次に検討したのが、国立国会図書館で日本経済新聞に記載された取得日の株価を調査する方法です。
20年も前の新聞となるとマイクロフィルムでの保管となっており、手動でフィルムを巻き取りながら画面上で記事を探すのは、思った以上に大変で、時間がかかりました。
小さな文字の中から会社名を探し出し、該当のページを印刷して、株価の確認完了!!と思ったのも束の間でした。
帰りの電車の中で、印刷した新聞を確認したところ、なんと掲載されていた株価は取得日の翌日のものだったのです。
新聞への掲載は翌日となるため、確認しなければならないのは、株の取得日の翌日の新聞でした。冷静に考えれば当然のことですが、焦っていたせいか日付を1日間違えてしまいました。国会図書館での苦労が水の泡となり、意気消沈しました。
その後、改めて調べてみると「日経新聞縮刷版」という、毎日の新聞を縮小して月ごとにまとめた資料があることを知りました。近所の図書館に当時の縮刷版が保管されていることがわかり、翌日早速図書館に向かいました。
「日経新聞縮刷版」には株価情報も漏れなく掲載されており、今度は間違いなく取得日の株価であることを確認し、該当部分を印刷して株価の確認を終えることができました。幸いにも前日の株価と同額でしたが、しっかりと確認できたことで一安心です。
まとめ
持株会で取得した株式の取得費が不明な場合には、持株会口座から名義書換えが行われた日を取得日とすることができる。
過去の株価は、まずインターネットで調査し、イレギュラーなケースで情報が見当たらない場合には、“取得日の翌日の日本経済新聞”を確認することで把握できる。その際、「日経新聞縮刷版」を確認すると効率的である。
今回の経験が、同様のケースに直面された方の一助となれば幸いです。